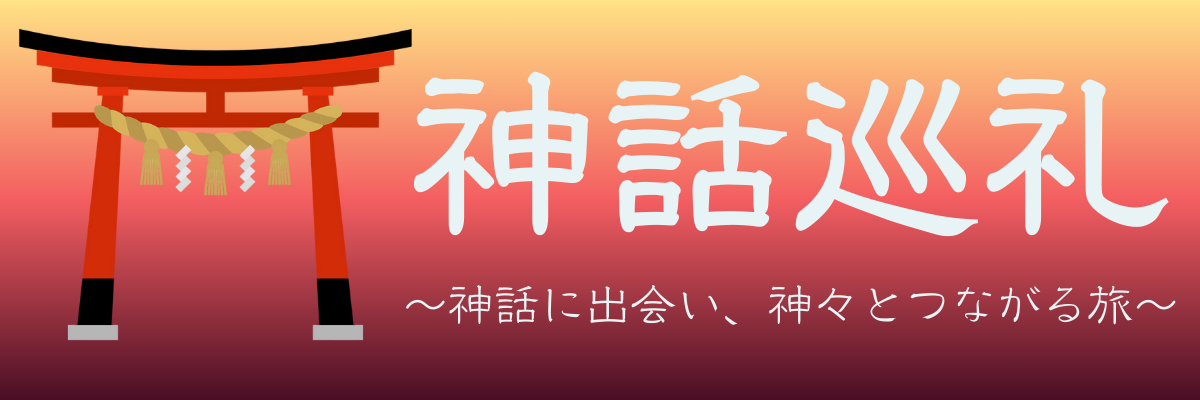禊の中から生まれた、知られざる四柱の神
『古事記』の物語の中で、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国から戻り、自らの穢(けが)れを祓うために行った禊(みそぎ)は、日本神話における大きな転換点となりました。
この禊の場面では、多くの神々が生まれますが、その中でも特に重要な役割を担う神々がいます。
それが…
祓戸四神(はらえどのししん)
この四柱の神々は、『古事記』本文には神名として登場しません。
しかし、祝詞(のりと)の中でも特に重要とされる「大祓詞(おおはらえのことば)」において、人々の罪や穢れを段階的に祓い清める存在として明確に語られています。
彼らは川と海と風、そして異界を舞台に、人々の心身を浄める見えざる神々の働きを象徴しているのです。
※本記事は、特定の信仰や解釈を断定するものではなく、日本神話や神社文化を理解するための参考情報としてまとめています。
穢れを祓う、川と海と風の神々
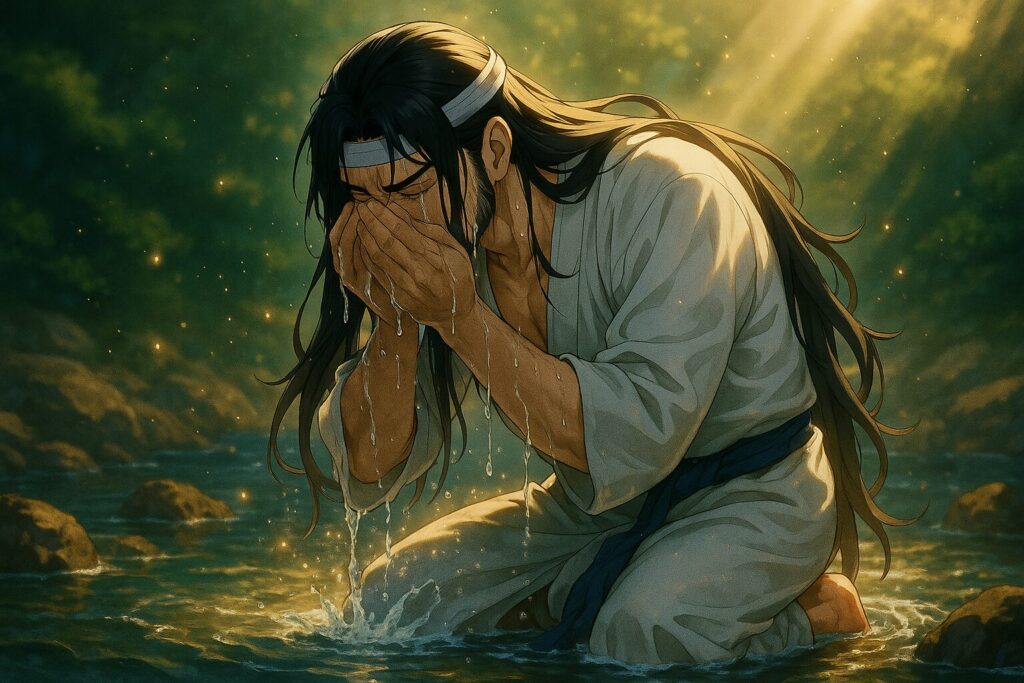
黄泉(よみ)の国から戻った伊邪那岐命は、その身にまとわりついた重く黒い穢れを感じていました。
そのままでは、神々の世界へ戻ることはできません。
彼は、筑紫の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小戸(おど)の阿波岐原(あはぎはら)の清らかな水が流れる地へとたどり着きます。
風がやさしく吹き、川の瀬が光を受けてきらめいていました。イザナギは衣を脱ぎ、その身を水に沈め、深く息を吐き出します。
その瞬間、水面に波が立ち、川瀬が眩しく光を帯びます。
穢れを押し流す流れとともに、四柱の神々が姿を現したのです。
最初に現れたのは、瀬織津比売神(せおりつひめのかみ)。
彼女は速川(はやかわ)の瀬を渡り、すべての禍事(まがごと)・罪・穢れを一気に大海原へと押し流していきます。
次に、速開都比売神(はやあきつひめのかみ)が海の河口に姿を現しました。
彼女は流れ着いた罪や穢れを、すべて飲み込み、深い海の底へと沈めます。
すると、海の向こうから気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)が風となって吹き渡り、飲み込まれた穢れを根の国・底の国(ねのくに・そこのくに)へと吹き放ちます。
最後に、速佐須良比売神(はやさすらひめのかみ)が現れました。
彼女は、異界に送られた穢れを漂わせ、遠く遠くへと流し去り、二度と戻らぬように消し去ってしまいます。
祓戸四神の働きは、自然の浄化の摂理そのものを映し出していました。
祓戸四神とは

祓戸四神(はらえどのししん)とは、神道において祓い(はらえ)を司る四柱の神々の総称です。
『古事記』『日本書紀』には神名として記載されていませんが、祝詞の中の「大祓詞」において、人々の罪や穢れを段階的に清める重要な存在として登場します。
| 神名 | 役割(「大祓詞」に基づく) |
| 瀬織津比売神(せおりつひめのかみ) | 穢れを速川の瀬から大海原へ流し出す |
| 速開都比売神(はやあきつひめのかみ) | 大海原で流されてきた穢れをすべて飲み込む |
| 気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ) | 穢れを根の国・底の国へ息吹で吹き放つ |
| 速佐須良比売神(はやさすらひめのかみ) | 穢れを漂わせて失わせ、完全に消滅させる |
この四神の働きは、川 → 海 → 異界という流れをなぞることで、自然界と人間の心身の浄化のプロセスを象徴しています。
記紀に見えぬ三神 ― 謎と諸説
祓戸四神のうち、速開都比売神(はやあきつひめのかみ)は『古事記』の神産みに「速秋津日売神(はやあきつひめ)」として登場しますが、他の三神、瀬織津比売神・気吹戸主神・速佐須良比売神は、記紀に一切登場しません。
この「記載の欠落」は、古来より多くの議論と憶測を生んできました。
『神道五部書』の説
中世の伊勢神道で作成された『神道五部書』というものがあります。
その中では、この三神を天照大神(あまてらすおおみかみ)や豊受大神(とようけのおおかみ)の荒魂(あらみたま)と関連づけています。
- 瀬織津比売神=天照大神の荒魂、八十枉津日神の別名
- 気吹戸主神=神直毘・大直毘神の別名、豊受神または月神の荒魂
- 速佐須良比売神=須佐之男命と関連
しかしこれらは後世の創作であり、史料的信頼性は低いとされています。
特に瀬織津比売神を内宮荒祭宮の祭神とする記述は後付けの設定であり、学術的には否定的な見解が主流です。
江戸国学の憶測と影響
江戸時代の国学者・本居宣長や平田篤胤らも、この三神を既存の神々と結びつけようとしました。
- 禍津日神=瀬織津比売
- 伊豆能売神=速開津比売
- 直毘神=気吹戸主
- 須勢理毘売命=速佐須良比売(根の国に関係することから)
※上記の神々は「三貴子の誕生」の記事で登場します。
これらは大胆な同定でしたが、根拠に乏しく、多くは「こじつけ」とされています。
しかし、瀬織津比売=禍津日神説などは後世に広まり、今でも一部で「通説」のように語られることがあります。
記紀の不完全性という見解
一方で、近年では「記紀が伝承を完全に網羅したわけではない」という視点が注目されています。
古事記と日本書紀の間でも互いに記載されていない神々や伝承が存在することから、祓戸の三神は単に別系統の伝承に属する神々であった可能性が高いとされます。
「大祓詞」の四神のうち三神が記紀に見えないのは不自然ではなく、記載されなかっただけ
の話ではないのか。
この見解が、もっとも穏当で説得力のある立場といえるでしょう。
瀬織津姫=天照大神説
現代の一部の神秘思想家や研究者の間では、瀬織津比売神を天照大神の「もう一つの側面」、すなわち荒魂・影の光として捉える説があります。
岩戸隠れの神話と、瀬織津姫が長らく封印されてきたとされる伝承を重ね、両者を統合的に解釈する流れも生まれています。
天照大神と瀬織津姫の「夫婦神」説

天照大神が実は男神であり、瀬織津姫はその妻神であるという興味深い説も存在します。
この解釈の背景には、伊勢神宮・外宮に祀られている
豊受大神(とようけのおおかみ)=瀬織津姫という見方があります。
豊受大神は、内宮の天照大神に食事を供する神として知られています。
しかし、「なぜ“食事の神”が伊勢神宮という国家最高の神社で、これほど大きく祀られているのか」という点がしばしば議論の的となってきました。
本来、より顕著な神威を持つ神々は他にも多数存在します。
それにもかかわらず、豊受大神が外宮の主祭神として特別な位置を占めていることは、単なる「食事の神」という役割以上の存在であることを示唆していると考える研究者もいます。
そこで浮上してきたのが、天照大神と瀬織津姫(=豊受大神)を「夫婦神」とみなす説です。
もし天照大神が男神であり、瀬織津姫がその妻であったとすれば、伊勢神宮という日本神道の頂点において、両者が並び祀られていることにも納得がいきます。
この視点から見ると、外宮の存在は単なる付属ではなく、天照大神と対をなす存在=正妻神の社としての意味を帯びてくるのです。
信仰実践 ― 祓戸社と大祓詞
祓戸四神は、理論や神話の中だけでなく、現実の神社信仰でも重要な役割を担っています。
多くの神社には、本殿の前に「祓戸社(はらえどしゃ)」が設けられています。
参拝者はまずここに参拝し、身と心を清めてから本殿へ向かうのが正式な作法です。
神職によって唱えられる「祓詞」や「大祓詞」では、祓戸四神の名と役割が順に語られ、穢れを祓い清めるよう祈願します。
祓串(はらえぐし)を左・右・左と振って身を祓う所作も、この信仰の具体的な表れです。
祓戸四神は、目に見えない場所で常に人々を清め、神域への道を開いてくれる存在なのです。
まとめ
祓戸四神(はらえどのししん)は、『古事記』には名を残さないものの、「大祓詞(おおはらえのことば)」において重要な役割を担う神々です。
川から海、そして異界へと穢れを流し清める四柱の働きは、自然の循環と人の浄化を重ねた祓いの本質そのもの。
彼らは祓詞や祓戸社での信仰を通じ、今も人々の心身を清め、神々との道を開く存在として息づいています。