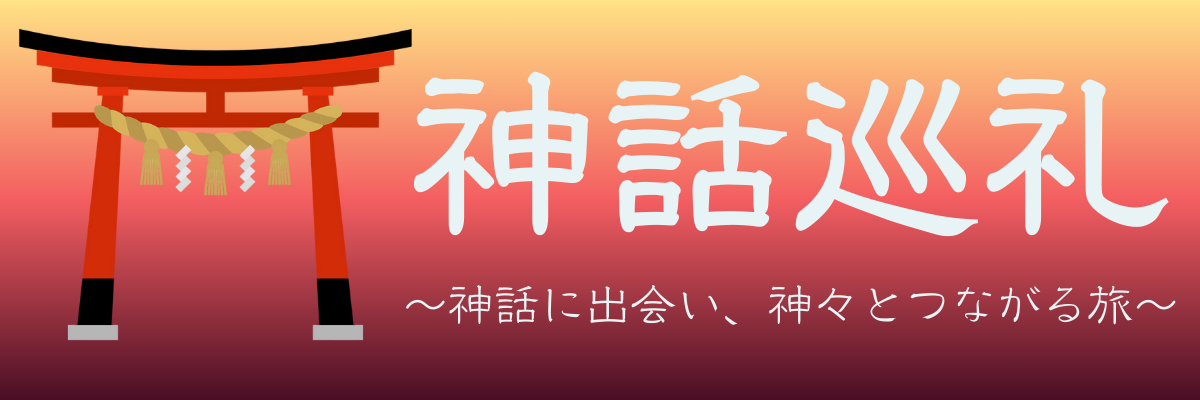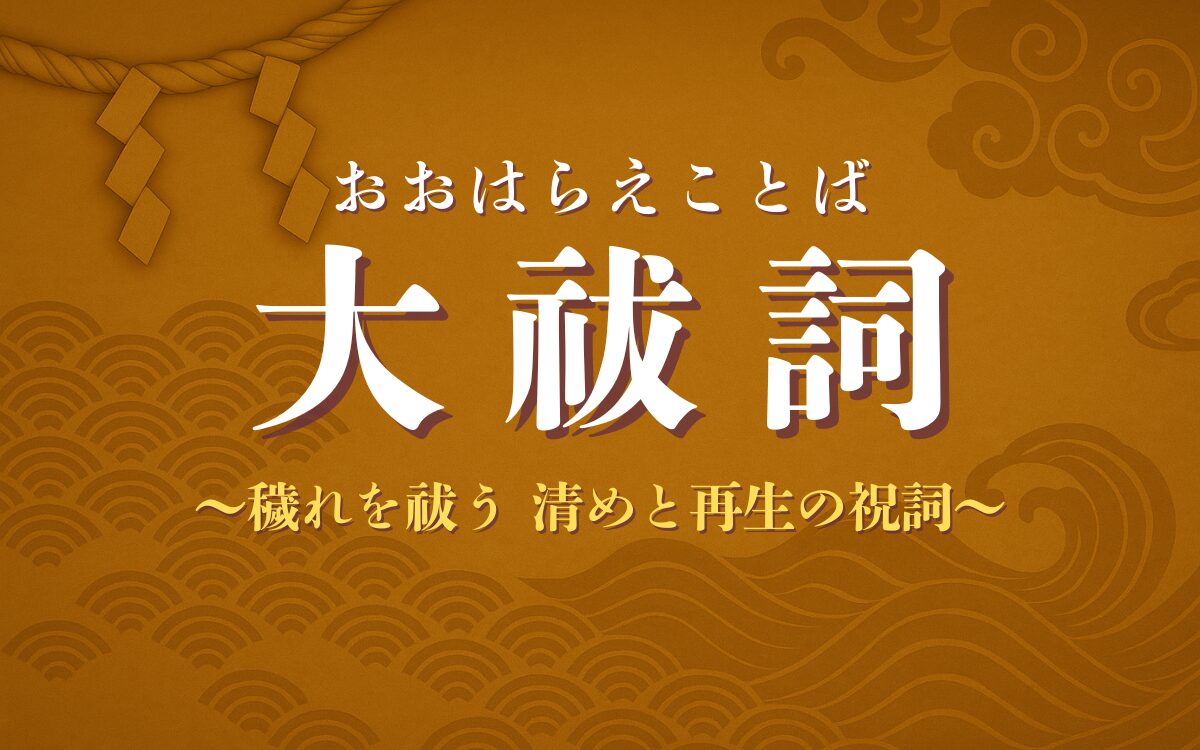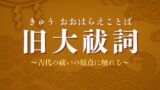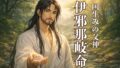前回の記事では、日常の中で心や場を清めるための「祓詞(はらえことば)」をご紹介しました。今回取り上げるのは、その祓詞よりも長く力強い祝詞、「大祓詞(おおはらえことば)」 です。
大祓詞は、6月と12月の晦日(みそか)に全国の神社で行われる「大祓(おおはらえ)」という儀式で奏上される祝詞です。
半年ごとに、心身や社会に積もった穢れを祓い、新しい気持ちで次の半年を迎えるための、日本人の再生の祈りともいえる詞章です。
現在、神社で一般に奏上されている大祓詞は、古式から一部を省略した現行版(戦後の標準形)が使われています。
ここでは、その全文と現代語訳を紹介し、現代の大祓詞の意味と役割を解説します。
※本記事は、特定の信仰や解釈を断定するものではなく、日本神話や神社文化を理解するための参考情報としてまとめています。
現行の大祓詞とは

大祓詞はもともと、927年完成の『延喜式』に収められた古式の祝詞(旧大祓祝詞)を原型としています。
しかし、戦後の神社制度の変化や社会背景を受けて、天津罪・国津罪の列挙部分が省略された短縮形が神社本庁によって標準化されました。
現在は全国の神社でこの形が使われています。
短縮型になった経緯は別記事でお話ししていきます。
この現行版は、一般の参列者も唱えやすく、神職とともに声を合わせる形式も多く見られます。
「半年に一度、心と身体、場を清め直す」という意味では、現代でも変わらず大切にされている祈りの時間です。
大祓詞(全文)
大祓詞は4つの章で構成されています。
各章に分けた大祓詞の全文をご紹介していきます。
【第一章 皇御孫神の降臨】
高天原に神留まり坐す
皇が陸神漏岐 神漏美の命以ちて
八百万の神等を
神集へに集へ給ひ 神議に議り給ひて
我が皇御孫の命は
豐葦󠄂原の瑞穂の国を安国と平らけく
知ろし召せと言依さし奉りき
此く依さし奉りし国中に荒󠄄ぶる神等をば
神問はしに問はし給ひ 神掃ひに掃ひ給ひて
語問ひし磐根・樹根立ち草󠄂の片葉󠄂をも語止めて
天の磐座放ち天の八重雲を伊頭の千別に千別て
天降し依さし奉りき
【第二章 皇御孫神の統治と罪の発生】
此く依さし奉りし四方の国中と
大倭日高見の国を安国と定め奉りて
下つ磐根に宮柱太敷き立て 高天原に千木高知りて
皇御孫の命の瑞の御殿仕へ奉りて
天の御蔭 日の御蔭と隱り坐して
安国と平らけく知ろし召めさむ
国中に成り出でむ天の益人等が 過ち犯しけむ
種種の罪事は天つ罪 国つ罪 許許太久の罪出でむ
【第三章 大祓の実施】
此く出でば 天つ宮事以ちて
天つ金木を本打ち切り 末打ち断ちて
千座の置き座に置き足らはして 天つ菅麻󠄁を本刈り断ち
末刈り切りて 八針に取り辟きて
天つ祝詞の太祝詞事を宣れ
此く宣らば 天つ神は 天の磐門を押し披きて
天の八重雲を伊頭の千別に千別て聞こし召さむ
国つ神は高山の末・短山の末に上り坐して
高山の伊褒理・短山の伊褒理を搔き分けて聞こし召さむ
【第四章 罪が消えるまでの経緯】
此く聞こし召してば 罪と云ふ罪はあらじと
科戸の風の 天の八重雲を吹き放つことのごとく
朝の御霧・夕の御霧を朝風・夕風の吹き払ふことのごとく
大津辺に居る大船を舳解放ち艫解放ちて
大海原に押し放つことのごとく
彼方の繁木が本を 焼鎌の敏鎌以ちて打ち掃ふことのごとく
遺る罪はあらじと 祓へ給ひ清め給ふことを
高山の末・短山の末よりさくなだりに落ち激つ
速川の瀬に坐す瀬織津比売と云ふ神
大海原に持ち出でなむ
此く持ち出で往なば
荒潮の潮の八百道の八潮道の潮の八百会に坐す
速開都比売と云ふ神
持ちかか呑みてむ
此くかか呑みてば 息吹き処に坐す気吹戸主と云ふ神
根の国・底の国に息吹き放ちてむ
此く息吹き放ちてば根の国・底の国に坐す
速佐須良比売と云ふ神 持ち流離ひ失ひてむ
此く佐須良ひ失ひてば罪と云ふ罪はあらじと
祓へ給ひ清め給ふことを
天つ神・国つ神 八百万の神たち共に聞こし召せと白す
現行大祓詞の現代語訳
【第一章 皇御孫神の降臨】
高天の原にいらっしゃる男女の神のお言葉によって
八百万の神が集められ、会議を行い
瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)は豊葦原の瑞穂国(この世界)を平和に治めなさいとおっしゃった。
荒ぶる神は次々に問い正され、次々に掃いのけられ
騒がしかった草木も、ものを言うことをやめさせて
天上の御座所を後にし、空の多くの雲を掻き分けて
天上からこの世界に降臨なさった。
【第二章 皇御孫神の統治と罪の発生】
地上の国の中心として大和の国を定められ
地下の大きな岩に太い柱を立てて
高天の原に向かって瓊瓊杵尊の宮殿をお造り申し上げ
瓊瓊杵尊はここに住み、平和な国としてお治めになった。
国の中に生まれてくる人間が過ち犯す罪には
天つ罪や国つ罪などの多くの罪が出てくるだろう
【第三章 大祓の実施】
このように多くの罪が出てくれば
天から伝わった儀式に従って
金属のように硬い木を切り、根本を打ち断って
台の上に置いて、菅の根本を刈り取り
末を刈り取り細かく裂いて
天の立派な祝詞を読みなさい
このように祝詞を奏上すれば、天つ神は天の岩戸の扉を開けて
幾重にも重なる雲を掻き分けてお聞きになるでしょう
国つ神も高い山や低い山の頂上に登って
雲を掻き分けてお聞きになるでしょう
【第四章 罪が消えるまでの経緯】
これを神々がお聞きになったならば、罪という罪はなくなり
その様子は風が幾重にも重なる雲を吹き飛ばすようで
朝の霧も夕方の霧も、朝の風、夕の風が吹き飛ばすようで
大きい港に居る船を解き放って
大海原へ押し放つようで
遠く向こうの茂った草木を焼き入れをした鋭利な鎌で刈りとるように
残る罪はなくなるでしょう
このように祓い清めた罪は
高い山や低い山の頂上から流れ落ちる
流れのはやい川にいらっしゃる瀬織津姫という神が
大海原までもっていくだろう
そして激しいたくさんの潮流が渦をなしているところにいらっしゃる速開津比売という神が
飲み込むだろう
それを息として吹き出すところにいらっしゃる気吹戸主という神が
根の国・底の国に吹き放つだろう
そして根の国・底の国にいらっしゃる速流離比売という神がそれをすっかりなくしてしまうだろう。
このように罪や穢れを祓い清めていただきますことを、謹んでお祈り申し上げます。
夏越の祓・年越の祓

現行大祓詞は、6月と12月の晦日に行われる大祓式で奏上されます。
- 6月:夏越の大祓(なごしのおおはらえ)
半年分の穢れを祓い、暑い季節を健やかに過ごすための祈り。茅の輪くぐりが象徴的です。 - 12月:年越の大祓(としこしのおおはらえ)
1年の罪や穢れを祓い、新しい年を清らかな心で迎えるための儀式。人形(ひとがた)に息を吹きかけ、自分の穢れを託して流す習わしもあります。
このとき神職が奏上するのが、今回紹介した「現行大祓詞」です。
まとめ
現行の大祓詞は、戦後の神社制度の中で一般の参列者にも広く親しまれる形に整えられました。
罪や穢れを具体的に列挙する部分は省略されていますが、神々の力によってあらゆる穢れが祓われ、清らかな心で新たな節目を迎えるという本質は変わりません。
半年に一度、大祓詞を唱え、心と身体、場をリセットする時間を持つ。
これは現代人にとっても、とても意義深い習慣です。
もし、何か心に引っかかる出来事があった時は、ぜひ大祓詞を唱えてみて下さい。
物事がうまくいったり、心が軽く感じられるかもしれません。
次回予告
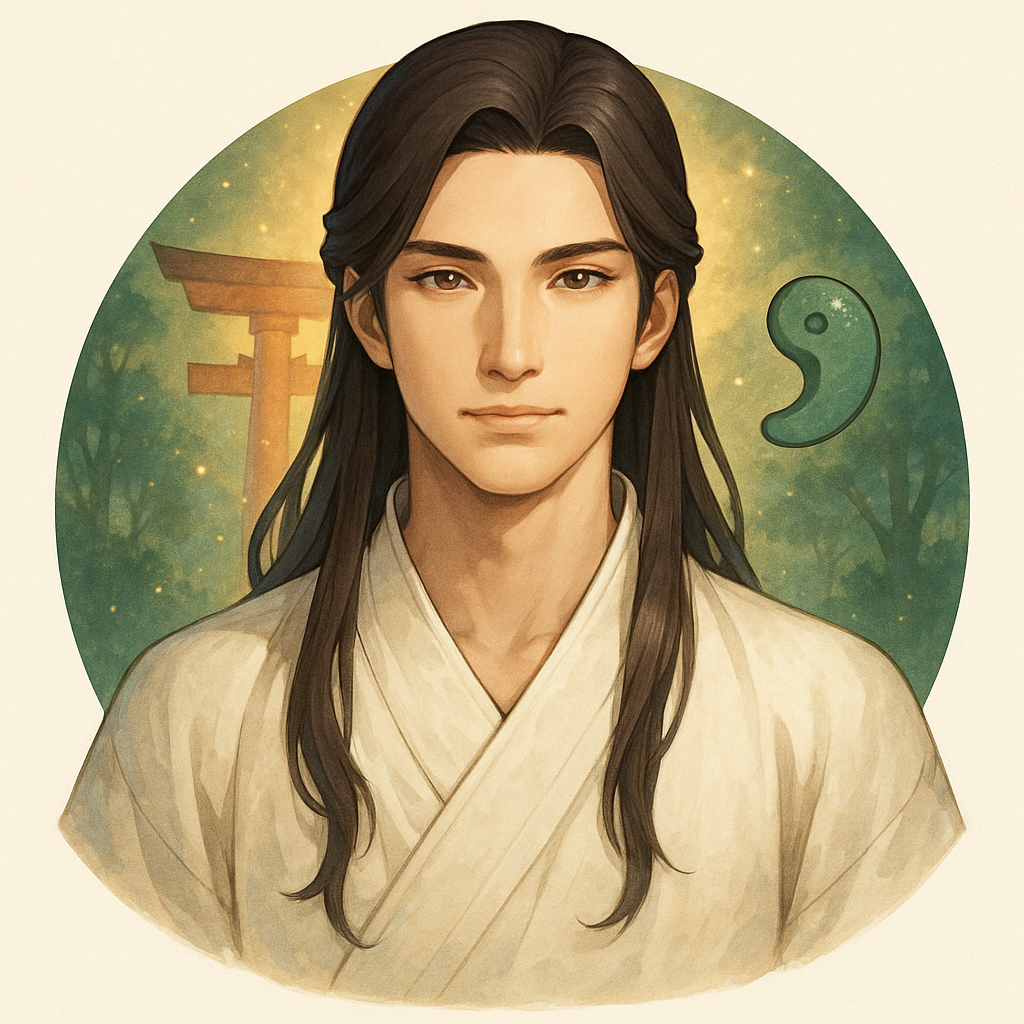
次回の記事では、今回の「現行版」の元となった『延喜式』収録の 「旧大祓祝詞 」を取り上げます。
そこには現代では省略されている「天津罪・国津罪」の列挙があり、日本人の祓いの原型が刻まれています。
なぜこの部分が戦後に削除されたのか…
その歴史的背景もあわせて解説します。
さらに祝詞を深く学びたい方へ
今回ご紹介した「大祓詞(おおはらえのことば)」をはじめ、古来より伝わるさまざまな祝詞をより深く知りたい方には、こちらの一冊をおすすめします。
『物部神道祝詞集』は、古神道の流れを受け継ぐ貴重な祝詞を体系的にまとめた一冊です。
祝詞だけではなく、般若心経や不動明王のお経なども載っています。
神道の精神性に触れる入門書としても最適。
日々の祓い、感謝の祈り、そして神々とのつながりをより深く感じたい方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。