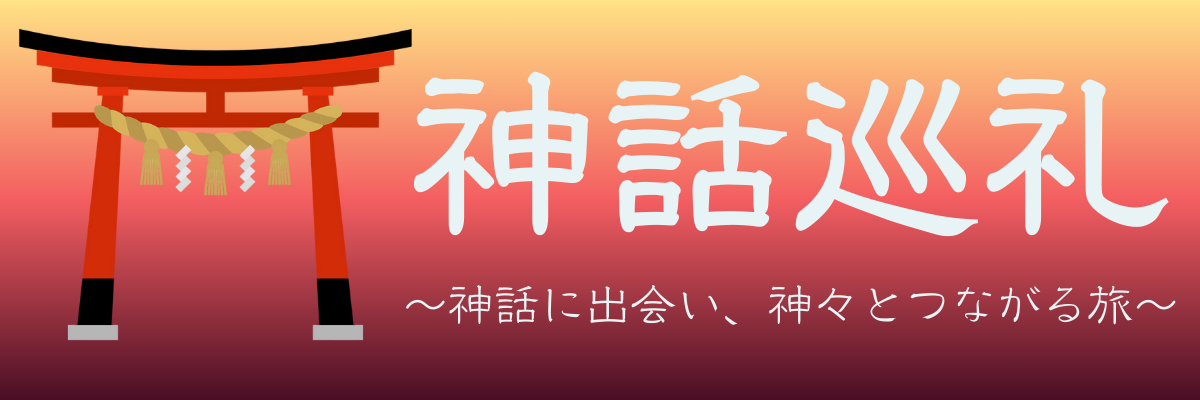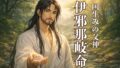千引の岩を境に、最愛の妻・伊邪那美命(いざなみのみこと)と永遠の別れを告げた伊邪那岐命(いざなぎのみこと)。
その身には、黄泉の国で受けた深い穢(けが)れがまとわりついていました。
「このままではならぬ……」
伊邪那岐命は心に決めます。
自らを清め、再び天上と地上の神々の世界に戻るために。
彼が向かったのは、筑紫の日向(つくしのひむか)にある 橘の小門の阿波岐原(たちばなのをどのあはぎはら)。
ここで、後の神話を大きく動かす「禊(みそぎ)」が始まります。
※本記事は、特定の信仰や解釈を断定するものではなく、日本神話や神社文化を理解するための参考情報としてまとめています。
禊の開始 ― 脱ぎ捨てから生まれる神々

伊邪那岐命は、身に着けていた衣や道具をひとつずつ脱ぎ捨てていきました。
するとそのたびに、神々が新たに姿を現します。
手にしていた杖からは、門戸を守る衝立船戸神(つきたつふなどのかみ)
帯を外すと、道を清め導く道之長乳歯神(みちのながちはのかみ)
衣を脱ぎ捨てると、病を祓う和豆良比能宇斯能神(わづらひのうしのかみ)
他にも、冠・腕輪・履物など、あらゆる身の回りのものから次々と神々が生まれました。
捨てるという行為そのものが、新しい命を生み出していく。
黄泉の穢れに包まれた身体から、逆に「清め」の力が溢れ出していったのです。
穢れから生まれる神々
しかし、黄泉の穢れは強大でした。
その穢れから生まれたのは、多くの災厄をもたらす 八十禍津日神(やそまがつひのかみ)、そしてさらに強大な災厄を象徴する 大禍津日神(おほまがつひのかみ) でした。
この二柱の神は、まさに「災いそのもの」
しかし、世界はそれをただ放置はしません。
すぐに、それを正す力を持つ神々が現れます。
神の意志をもって禍を正す 神直毘神(かむなおびのかみ)
その力を大きく拡張する 大直毘神(おほなおびのかみ)
そして清浄を司る女神 伊豆能売(いづのめ)
ここには、災いと浄化が対をなして生まれる、日本神話の深い死生観と「祓い」の思想が表れています。
水と海の神々
さらに禊の流れの中で、水と海を司る重要な神々が現れます。
まず、広大な海原を治める綿津見三神(わたつみのさんしん)
・底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)
・中津綿津見神(なかつわたつみのかみ)
・表津綿津見神(うはつわたつみのかみ)
そして、航海の安全を守る住吉三神(すみよしさんしん)
・底筒之男命(そこつつのおのみこと)
・中筒之男命(なかつつのおのみこと)
・表筒之男命(うはつつのおのみこと)
これらの神々は、海と船、そして人々の移動と繁栄を支える象徴です。
穢れを祓う水の力が、ここで命と文化の流れへと姿を変えていきます。
三貴子の誕生

そして…
禊の最終段階、伊邪那岐命が顔を洗ったとき。
最も尊い三柱の神々が生まれました。
左目を洗ったときに現れたのは、光輝く天照大御神(あまてらすおおみかみ)
右目からは、夜と秩序を司る月読命(つくよみのみこと)
鼻を清めたときには、荒ぶる力を持つ建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)が生まれました。
この「三貴子(みはしらのうずのみこ)」こそ、後に高天原・夜・海という三つの世界を担う存在。
伊邪那岐命の禊は、単なる浄化の儀式を超え、世界の秩序を担う神々を誕生させる神聖な創造の儀式となったのです。
委任と世代交代
伊邪那岐命は生まれた三貴子を大いに喜び、それぞれに役割を与えます。
天照大御神には、自らの首飾りを授け、天上界・高天原(たかまのはら)の統治を託します。
月読命には夜の世界を、建速須佐之男命には海原を治めるよう命じました。
こうして、国産み・神産みを担った創造神 伊邪那岐命から、次世代の神々へと世界の舞台が移り変わります。
これが、日本神話における大いなる「世代交代」の瞬間です。
次回予告
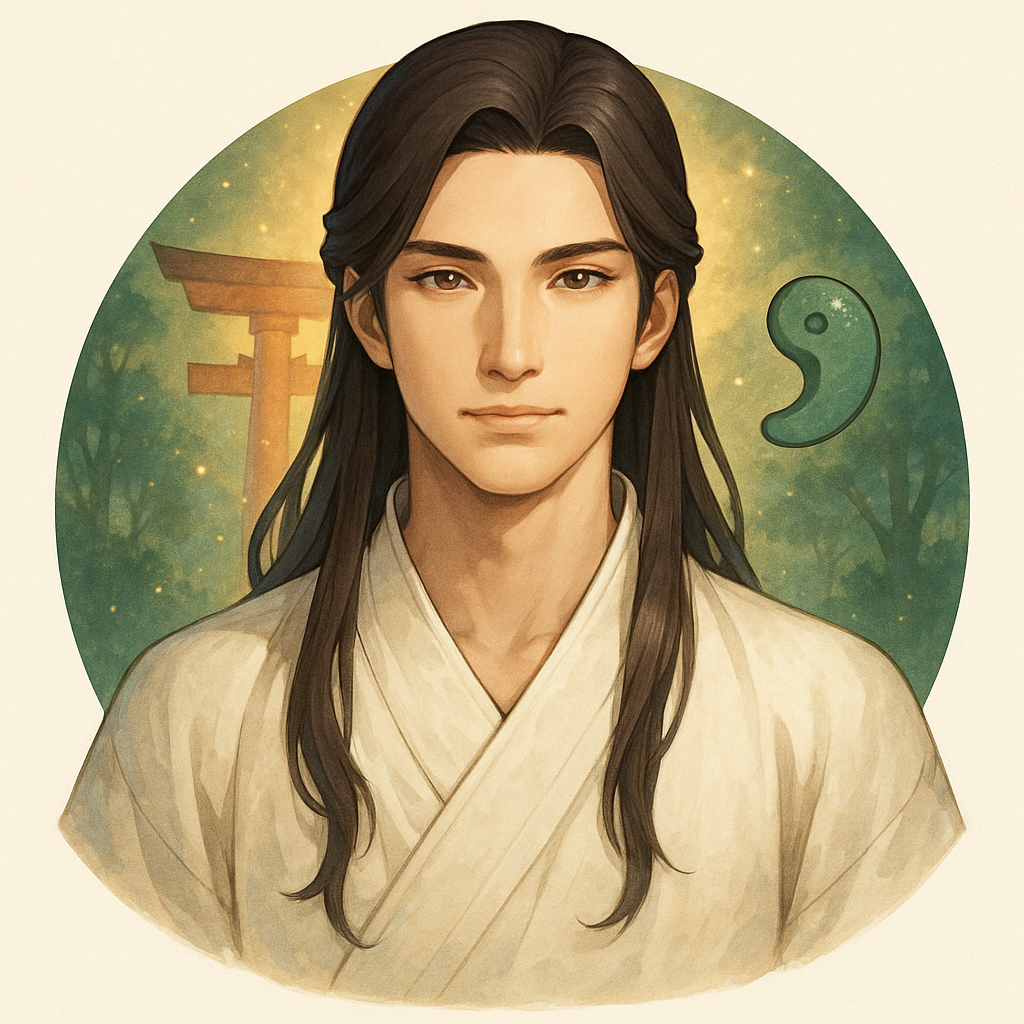
三貴子の登場により、神話の物語は新たな局面へ。
特に天照大神と須佐之男命の兄妹神の物語は、やがて国譲りや天孫降臨へとつながっていきます。
次回は、彼ら三柱がどのように世界を分かち、それぞれの神話を紡いでいくのかを見ていきましょう。