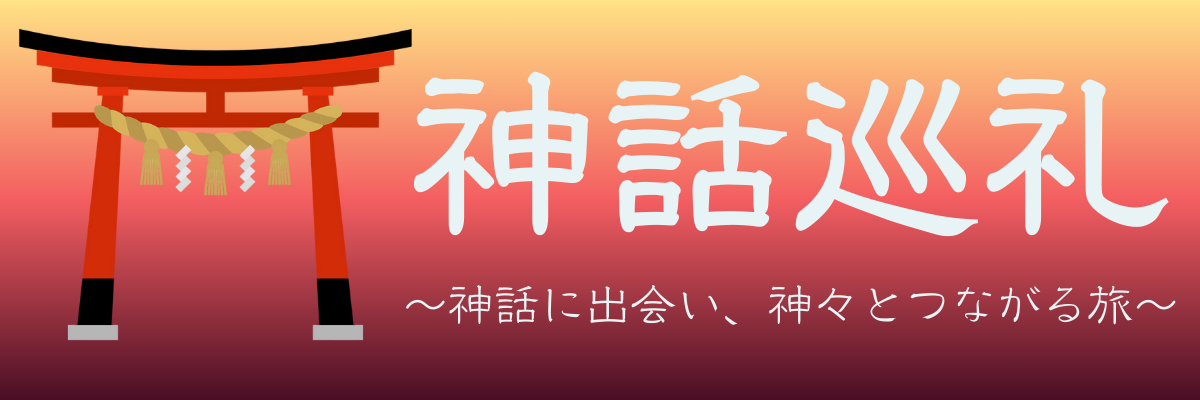前回の記事では、天地開闢の後に現れた「神世七代」の神々をたどり、その最後に登場した伊邪那岐命と伊邪那美命を紹介しました。
国土創造の使命を担うことになる二柱こそが、日本神話の大きな転換点となる存在です。
今回は、いよいよ伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)が天津神の命を受け、できたばかりの世界に秩序を与えていく「国産み」の物語が始まります。
二柱により、最初の島「淤能碁呂島(おのごろじま)」が誕生する瞬間から、日本列島が次々と生まれてくる壮大な神話の舞台が広がります!
※本記事は、特定の信仰や解釈を断定するものではなく、日本神話や神社文化を理解するための参考情報としてまとめています。
国産みの神話

天地開闢の後、高天原におられる神々(別天津神)は、まだ形を持たず漂う地上世界を見下ろしていました。
そこで神々は伊邪那岐命と伊邪那美命に命じます。

汝ら、この国を生み固めよ
ふたりは授けられた天の沼矛(あめのぬぼこ)で海をかき混ぜはじめます。
その矛先から滴り落ちた塩が固まってできたのが、最初の島「淤能碁呂島(おのごろじま)」です。
淤能碁呂島を拠点に、ふたりは日本という国作りを始めました。
婚姻の儀と大八島の誕生

国土を生むには、まず夫婦として結ばれ、男女の営みを行う必要がありました。
ふたりは島の中央に立つ天の御柱(あめのみはしら)を巡り、婚姻の儀式を行います。
しかし、伊邪那美命から伊邪那岐命へ声をかけてしまうという誤った作法をしていまったため、不完全な子が産まれてしまいます。
高天原の神々に相談したところ…

男神から先に声をかけるべきだった…
神々の言葉を受け、あらためてふたりは儀式をやり直しました。
今度は正しい手順で結ばれ、ようやく本格的な国産みが始まります。
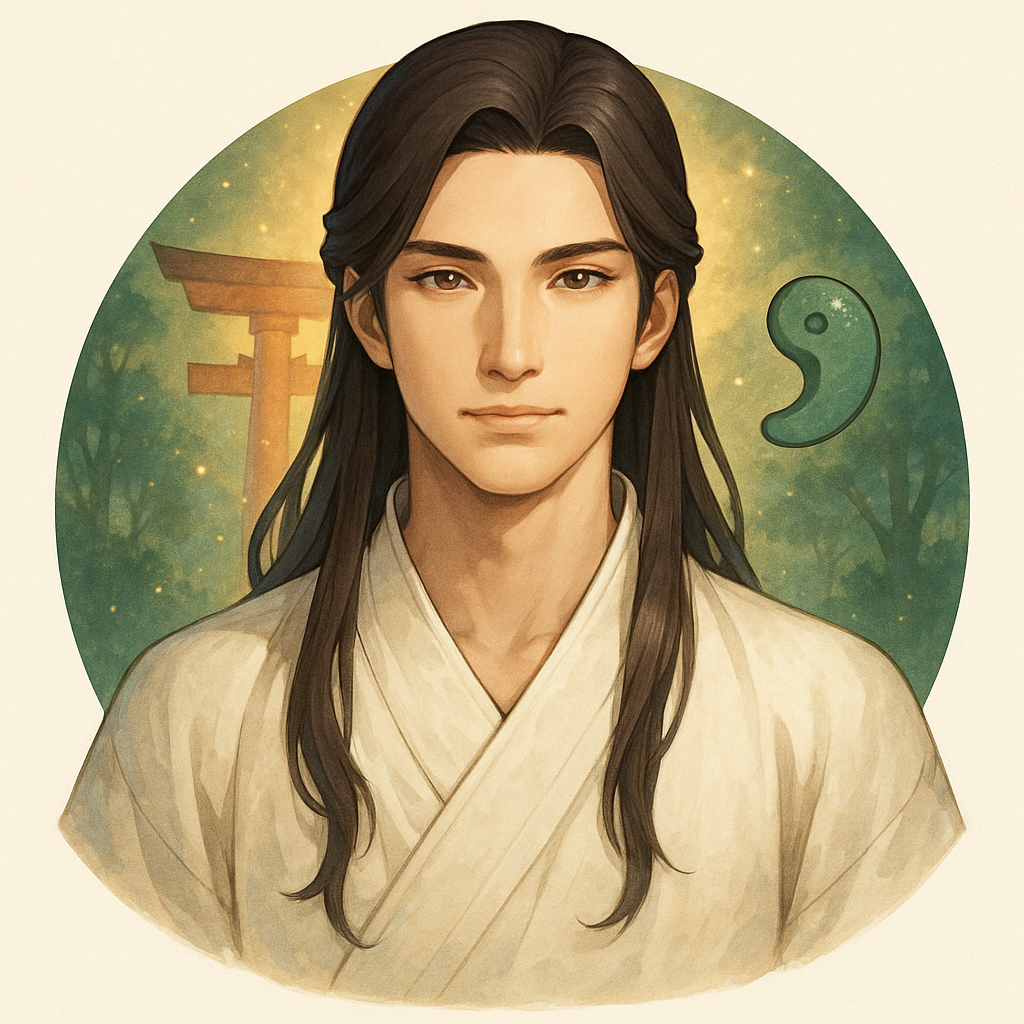
伊邪那岐命と伊邪那美命の婚姻の儀式にはもっと細かな物語があります。
その物語は、あらためて別記事でご紹介していきます。
やがて淡路島・四国・隠岐・九州・壱岐・対馬・佐渡・本州の八つの大きな島、「大八島(おおやしま)」が誕生しました。
さらに小豆島や吉備の児島、大島などの島々も次々と産まれていきました。
最終的には大八島と6つの島を合わせた14島をもって、日本という国産みは完結となりました。
日本の土台となる島ができた後も、山や川、木や風といった自然そのものを司る神々が現れ、日本列島は豊かな命を宿す地となっていきます。
この神話が伝えるもの
この国産みの神話には、日本人の価値観の基ともいえる思想が刻まれています。
最初の婚姻の儀式は、誤った順序で言葉をかけてしまい失敗となりました。
失敗を経て正しい順序で儀式を行い直したことは、「言葉には霊力が宿り、正しい言葉こそが世界を形づくる力となる」という言霊(ことだま)の信仰を表しています。
また、日本列島そのものが神によって産まれたという意識は、国そのものを神聖な存在とする感覚の基盤になりました。
こうした考え方は、後に天皇の神話的正統性や神道の世界観にもつながっていきます。
神道・神社に残る痕跡
この物語は、今も神社信仰の中に息づいています。
国産みの舞台となった淤能碁呂島は現在の淡路島(正確には離島の沼島)と言われており、淡路島には伊弉諾神宮が鎮座しています。
また、最初に生まれた不完全な子「蛭子(ひるこ)」は、後に恵比寿神と習合し、現在では商売繁盛の神として広く信仰されています。
淡路や出雲など、国産みの伝承地では、今も数多くの神社や祭祀がこの物語を伝え続けています。
現代へのメッセージ
国産みの物語は、現代を生きる私たちにも大切なことを伝えています。
日々交わす言葉には力が宿ることを意識し、丁寧に言葉を選ぶこと。
島々や自然を神として産んだ神話が示すように、自然を単なる資源ではなく「共に生きる存在」として尊ぶ視点を持つこと。
そして、たとえ失敗しても、やり直すことで正しい形にたどり着けるという、人生そのものに通じる教訓も感じさせてくれます。
次回予告
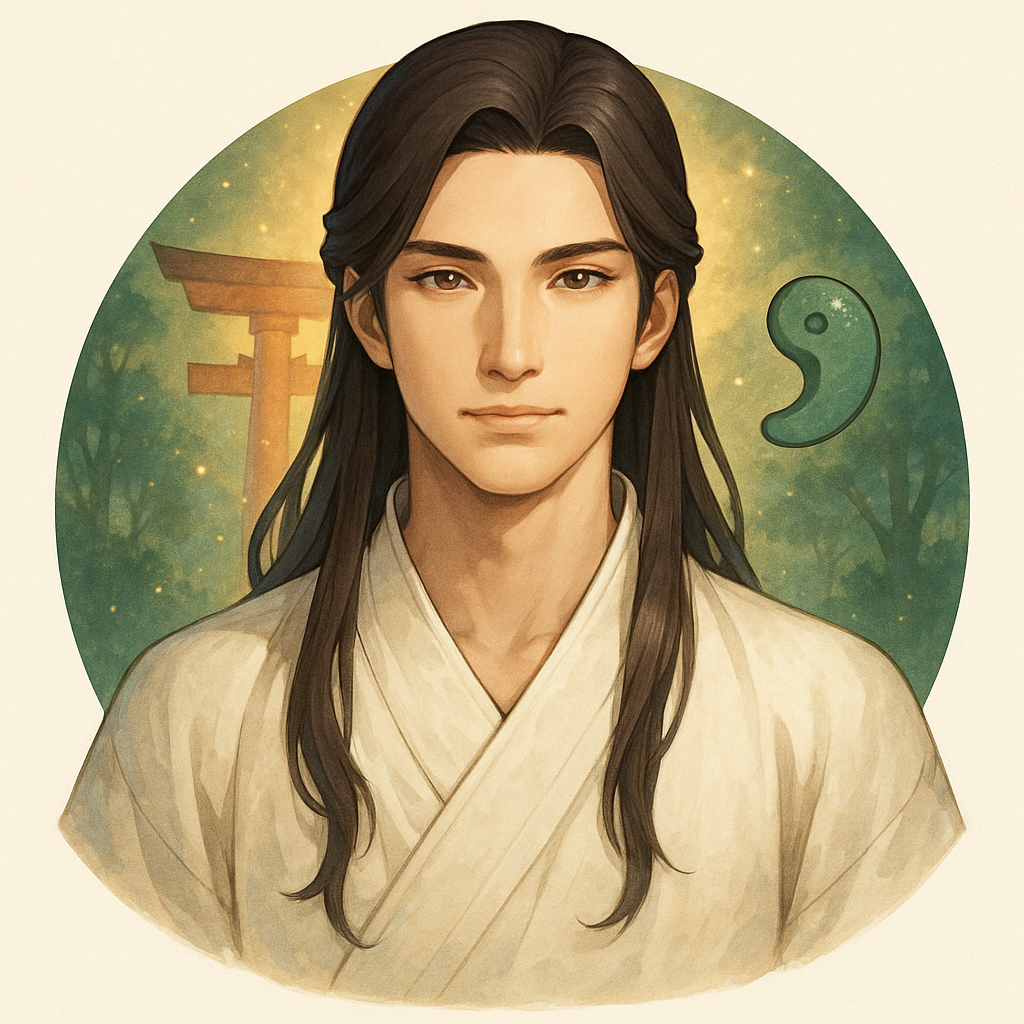
こうして国産みを終えた伊邪那岐命と伊邪那美命は、次に山や川、火や風といった神々を生む「神産み」へと進んでいきます。