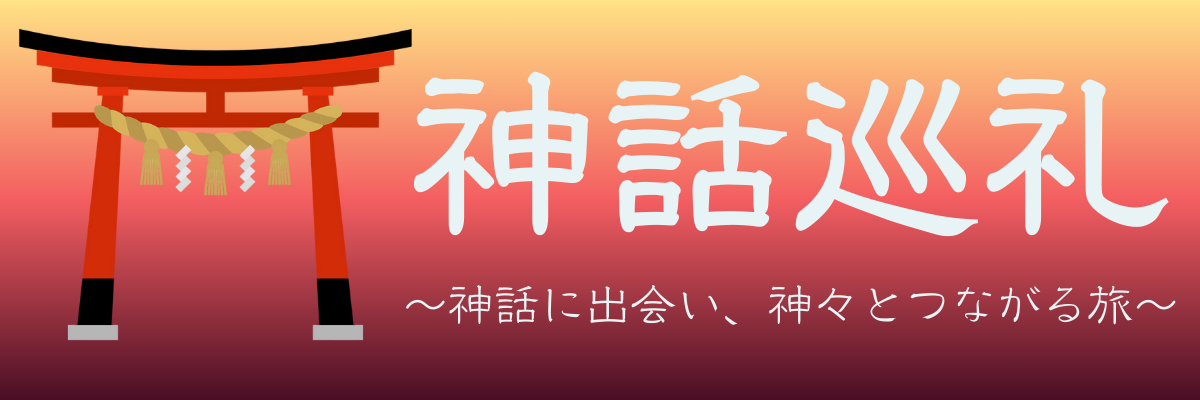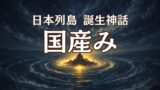前回は、天地開闢(てんちかいびゃく)の物語を紹介しました。
混沌とした世界から天と地が分かれ、その秩序の中で最初に現れたのが「造化三神(ぞうかさんしん)」
天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)
高御産巣日神(たかみむすひのかみ)
神産巣日神(かみむすひのかみ)
しかし、神々の登場はこれで終わりではありません。
三柱に続いて、さらに二柱の神が現れます。
・宇摩志阿斯訶備比古遅神
(うましあしかびひこぢのかみ)
・天之常立神(あめのとこたちのかみ)
これらの五柱をまとめて「別天津神(ことあまつかみ)」と呼びます。
天地が整えられる過程で、この別天津神たちが秩序の基盤を築き、その流れの先に「神世七代(かみのよななよ)」が登場するのです。
※本記事は、特定の信仰や解釈を断定するものではなく、日本神話や神社文化を理解するための参考情報としてまとめています。
神世七代とは?

古事記では、天地開闢と別天津神の後に「神世七代」が続きます。
これは七代にわたり現れる神々の系譜であり、最初は独神(ひとりがみ)、やがて男女神へと移り変わっていきます。
この変化は、宇宙の安定➡大地の生成➡生命誕生の準備という流れを象徴しているのです。
最初の二代【独神の系譜】
神世七代のはじめは「独神(ひとりがみ)」として現れる神々です。
独神とは、男女の区別を持たず、一柱だけで姿を現す神のことです。
造化の三神と同様、彼らは人のように目に見える活動はせず、ただ「存在」そのものが大いなる力を象徴している神様なのです。
それでは古事記に登場してくる順に七代の神様をみていきましょう!
第一代:国之常立神
国之常立神(くにのとこたちのかみ)
「国の基盤に常に立つ神」
大地そのものを司る神です。
変わることなく国土を支える存在であり、後の国土神の原点となります。
第二代:豊雲野神
豊雲野神(とよくもぬのかみ)
「豊かな雲の野の神」
大地に覆いかぶさる大空や豊かな雲、豊かな野を象徴する存在です。
国之常立神と合わせて、天地の「地」と「天」の基盤となります。
ここまでの二柱は前述したように独神で、対の神を持たない存在です。
ここからは男女神となります。
三代~七代【男女神の系譜】
ここから現れる神は、男女で一組となる神々です。
このペア神の登場によって、はじめて「生成」「繁栄」という男女の営みの原理が神話ではじまります。
第三代:宇比地邇神・須比智邇神
男神:宇比地邇神(うひぢにのかみ)
女神:須比智邇神(すひぢにのかみ)
「土の基盤」を意味する名前を持ち、大地を形作るエネルギーを象徴します。
名前の中にある比地、比智という文字には「泥」という意味があり、須は「砂」という意味があります。
男神である宇比地邇神の「宇比地」は「初泥(ういどろ)」と考えられており、「初めての泥土」という解釈がされています。
女神の須比智邇神は、須と比智で「砂と泥土」という解釈がされています。
ちなみに「邇」は親愛という意味があるようです。
第四代:角杙神・活杙神
男神:角杙神(つのぐいのかみ)
女神:活杙神(いくぐいのかみ)
「杙(くい)」とは地面に打ち込む杭のことです。
角杙・活杙の二柱は、まだ柔らかい大地を固め、世を安定させる杭打ちの神です。
杙(くい)は「植物が芽ぐむ」などの「くむ」とも読め、「角ぐい」とは角のように芽が出はじめるというような意味にもなります。
そして「活ぐい」は、生育しはじめるという意味となります。
この二柱の神によって、これから起こる「国産み」に欠かせない豊かな大地が出来上がったわけです。
第五代:意富斗能地神・大斗乃弁神
男神:意富斗能地神(おほとのぢのかみ)
女神:大斗乃弁神(おほとあのべのかみ)
大地を「大きな入り口」として整える神々です。
地の裂け目や通路を象徴し、天地を結びつける役割を担います。
「地」という文字は男性を意味し、「弁」という文字は女性を意味しています。
所説ありますが、この二柱には男女の「交合・出産」を象徴する神とも言われています。
第六代:淤母陀琉神・阿夜訶志古泥神
男神:淤母陀琉神(おもだるのかみ)
女神:阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ)
「おもだる」とは「完成した」という意味があり、地が形を整え完成したことを象徴しています。
さらに、「あやかしこね」には「畏れ多いながらも称賛する」という意味です。
国土が形を整え、美しさや秩序といった“精神的な豊かさ”が宿った段階を表す神々であり、次に登場する伊邪那岐・伊邪那美へと物語がつながっていきます。
日本書紀では、淤母陀琉が「面足」となり「顔立ちが整っている」という意味となっており、完成の対象を人体としている説もあるようです。
第七代:伊邪那岐命・伊邪那美命
男神:伊邪那岐命(いざなぎのみこと)
女神:伊邪那美命(いざなみのみこと)
「誘い合う男神、女神」という名を持ち、後に国産み、神産みを担う重要な存在です。
神世七代の最後に登場する事となりますが、伊邪那岐命と伊邪那美命によって、世界創造がここから大きく進んでいきます。
この二柱のストーリーは、あらためて「国産み」「神産み」の回でお話していきましょう。
神世七代が持つ意味

神世七代は、単なる神々の誕生を描いている訳ではありません。
独神は「大自然の根源的な力」を表し、男女神は「生命を生み出す働き」を象徴しています。
つまりこれは、宇宙の静から動への転換期を描いた章とも言えるのです。
神道は自然信仰で、山や川、木や岩も神として信仰してきました。
祭祀でも「天地自然の力を敬う」ことが基本とされています。
その背景にはまさにこの神世七代の思想が継がれています。
私たちが神社で祈るとき、背後にはこうした「自然の根源から命がつながっている」という感覚が生き続けているのです。
この物語が現代に伝えるメッセージ
神世七代の流れを見ていくと、私たちは大切なことに気づかされます。
独神は人の形や行動を持たない神々で、目に見えないものの尊さを教えてくれます。
現代でいえば「空気」や「水」、「大地の安定」といった、普段意識しないが欠かせない基盤を大事にすること。
男女神の登場は、すべての営みは「関係性」から始まる。
家族や社会、人と自然のつながりなしには未来は続かないことを示しているのではないでしょうか。
今の時代、環境問題や人間関係の分断が課題となり、社会問題へと発展しています。
神世七代の神々は、目に見えない自然への感謝と、つながりを育む調和の姿勢を、改めて思い出させてくれるのです。
次回予告、国生みの物語へ!
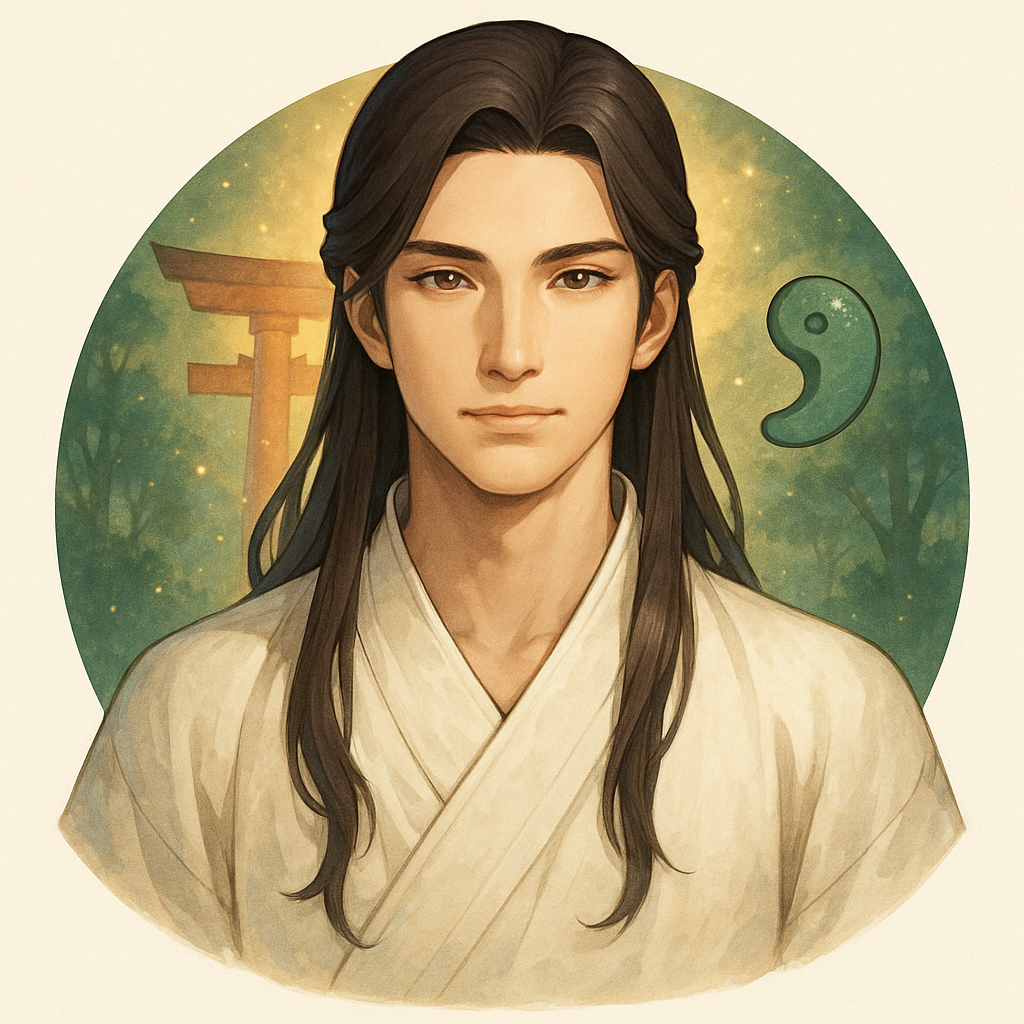
神世七代の物語を経て、いよいよ伊邪那岐命・伊邪那美命の二神の物語になります。
海をかき混ぜ、最初の島「オノゴロ島」を生み出す…
ここから「国生み」の壮大なドラマのスタートです!
次回は、その「国生み神話」をじっくりとひも解いていきましょう。