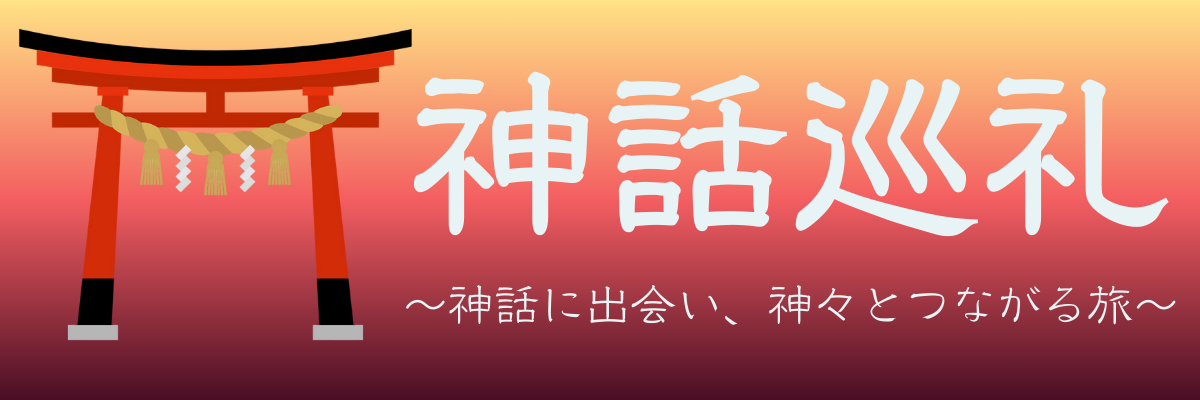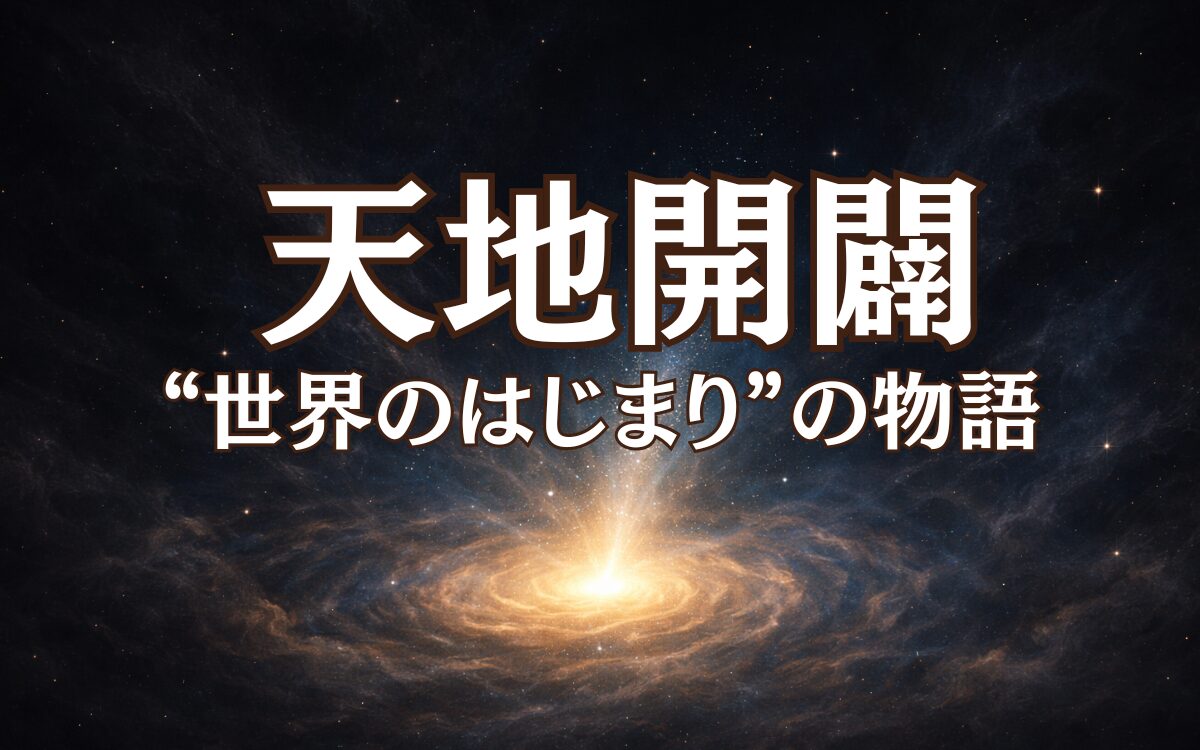これまでの記事では、まず『古事記』という書物の成り立ちから入り、神道や日本の根底にある世界観を整理してきました。
と順を追って理解を深めていただき…
ようやく「物語の本筋」へ入る準備が整いました。
そして、いよいよ今回から『古事記で語られる始まりの神話』をお届けします。
第一幕は、“世界が生まれる瞬間”、まさに神話の核ともいえる天地開闢(てんちかいびゃく)の物語です。
この神話は、ただの創生譚ではありません。
混沌とした世界に秩序が生まれ、見えない神々がその基盤を築いている、壮大なプロローグです。
そして何より、“この物語こそが日本人の自然観・言霊信仰・神道のルーツ”ともいえる重要なエピソード。
今回はそんな「始まりの物語」に耳を澄ませながら、世界がどのように形づくられ、神々はどんな思いで現れたのかを、旅するように紐解いていきましょう。
それでは、『古事記』天地開闢、世界の始まりを描く物語、スタートです!
※本記事は、特定の信仰や解釈を断定するものではなく、日本神話や神社文化を理解するための参考情報としてまとめています。
始まりの神

まだ天も地も分かれておらず、光も影も、昼も夜も存在しなかった頃…
世界は濁った水のように、混沌とした「ひとつの塊」として漂っていました。
やがて、その静寂の中に、ぽつりと「気配」が生まれます。
それは姿かたちを持たず、ただ在るだけの存在でした…
最初に現れたのは「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」
宇宙の中心にいて、宇宙を司る根源の神。
すべての始まりを見届ける「大いなる存在、大いなる静けさ」ともいえる存在です。
天之御中主神に続いて、
「高御産巣日神(たかみむすひのかみ)」
「神産巣日神(かみむすひのかみ)」と現れます。
この二柱の神様は「むすひ」と呼ばれる“生み出す力”を宿した神々です。
芽吹き、結び、育むなどのエネルギーを象徴していました。
三柱の神々は、人の目に映る姿を持ちません。
名を残してはすぐに姿を隠し、ただ世界の成長を静かに支えていく存在。
後に「造化三神」と呼ばれる、この神々の誕生こそ、天地が分かれる始まりでした。
そして、混沌とした世界は、少しずつ変化を始めていきます。
重い物は下へ沈み、大地となりました。
軽い物は上へ昇り、天となりました。
この分かれ目が「天地開闢」
世界の夜明けでした。
造化三神の神々が現れた後、さらに二柱の神が現れます。
- 宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)
…若々しい生命力を象徴する神。 - 天之常立神(あめのとこたちのかみ)
…天が揺るがず永遠に立ち続けることを象徴する神。
これら五柱をまとめて「別天津神(ことあまつかみ)」と呼びます。
古事記の天地開闢とは?
古事記が描く天地創造は、他の神話と比べると大きな特徴があります。
- 西洋の神話:神が天地を一瞬で創造する(例:旧約聖書の「光あれ」)
- 日本神話:天地は自然に分かれていき、その流れの中に神々が現れる。
つまり、日本人の自然観は「人間や紙が自然を支配する」のではなく、「自然そのものが神聖であり、その営みに神が寄り添っている」という考え方に根ざしています。
この感覚は、今も日本の神社に色濃く残っています。
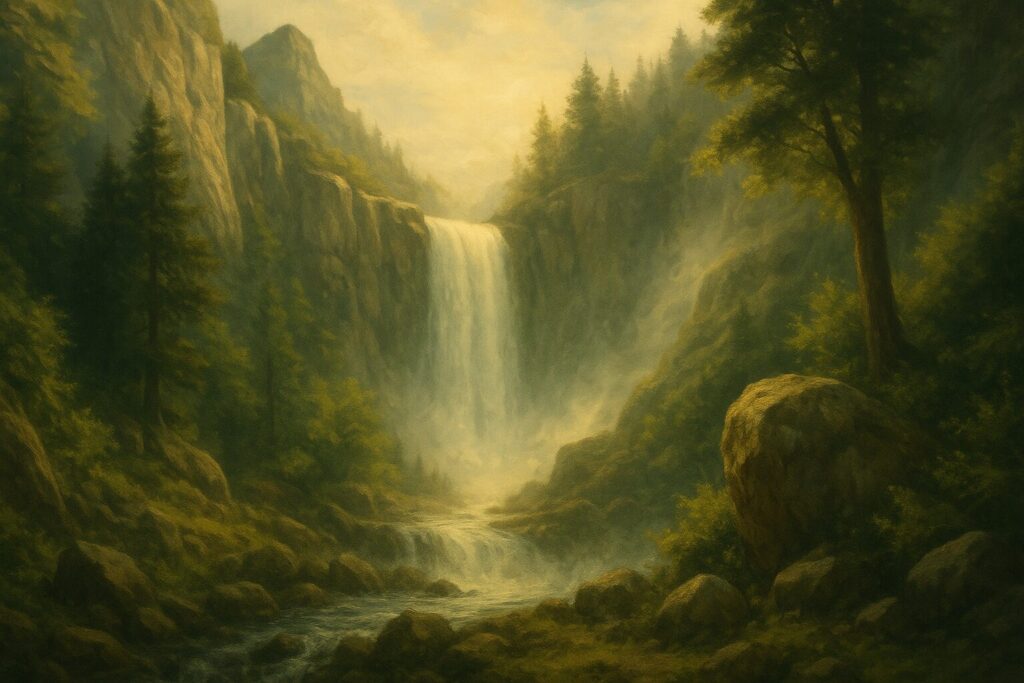
鳥居をくぐった先に鎮まるのは、必ずしも立派な建物ではなく、
ときには山そのもの、森、岩、滝が「神」とされます。
天地が分かれたその瞬間から「自然=神」という意識が息づいていたのです。
現代へのメッセージ
この神話が私たちに伝えるもの…
それは「秩序は混沌から生まれる」という真理ではないでしょうか。
人生の中でも、未来が見えず不安や迷いに包まれるときがあります。
しかし天地開闢の物語は、私たちにこう伝えているような気がします。
たとえ混乱の中にあっても、やがて必ず形は整い、道は開ける。
また「むすひ」の神々は「つながり」と「再生」も象徴しています。
人と人との縁、自然との調和、新しいものを生み出す力は、いつの時代も変わらず私たちの中に息づいています。
だからこそ今を生きる人々は、この神話を読み解くことで、
「自然と共にある生き方」「結びの力を信じる心」を思い出すことができるのです。
次回予告
天地開闢の神話は、ただの昔話ではなく、
自然と調和して生きてきた日本人の精神を今に伝える物語です。
混沌を恐れず、その中から芽生える“むすひ”の力を信じること。
それが、この古代の物語が現代に贈る大きなメッセージといえるでしょう。
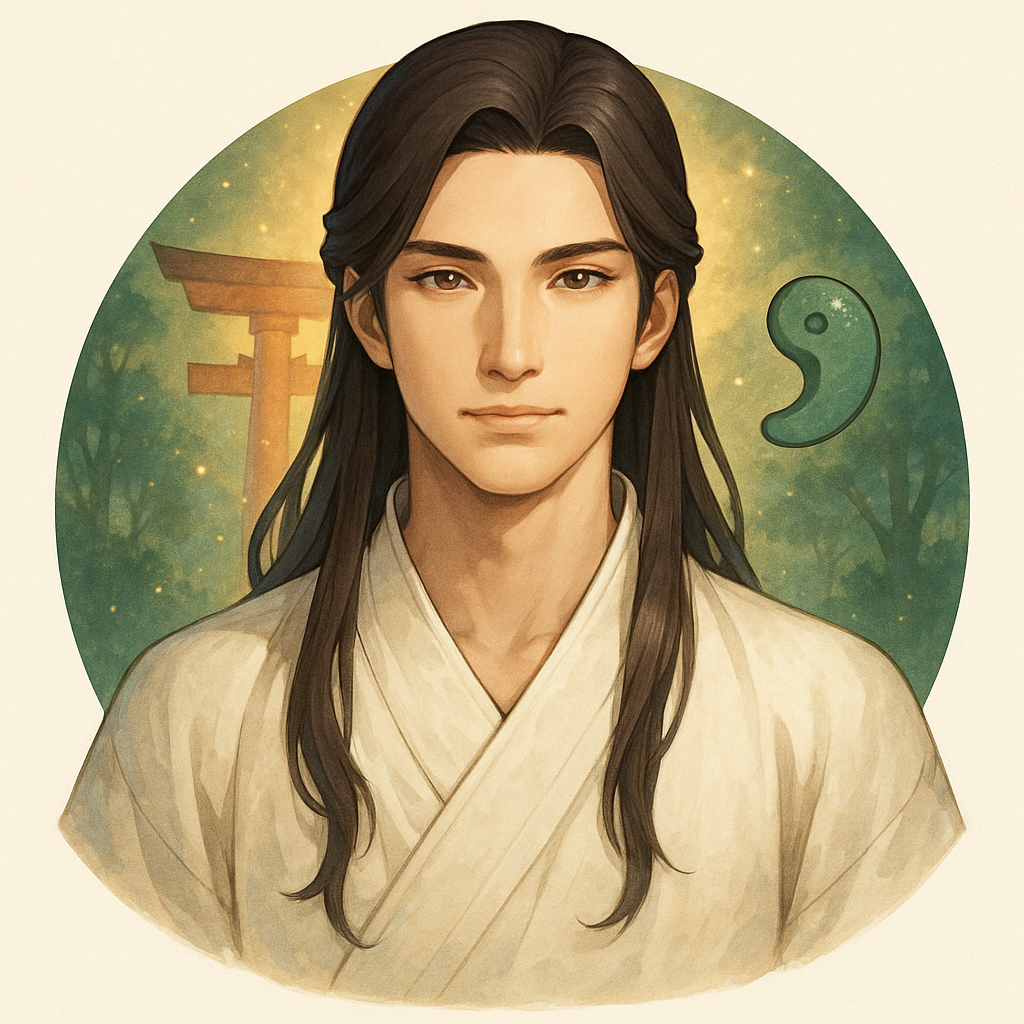
次回は天地開闢の後に続く、神道に今も影響を残す「別天津神」と「神世七代」の神々。
そしてついに、国生みへとつながる伊邪那岐・伊邪那美の登場です。
その橋渡しとなる「神世七代」の物語をひも解いていきます。