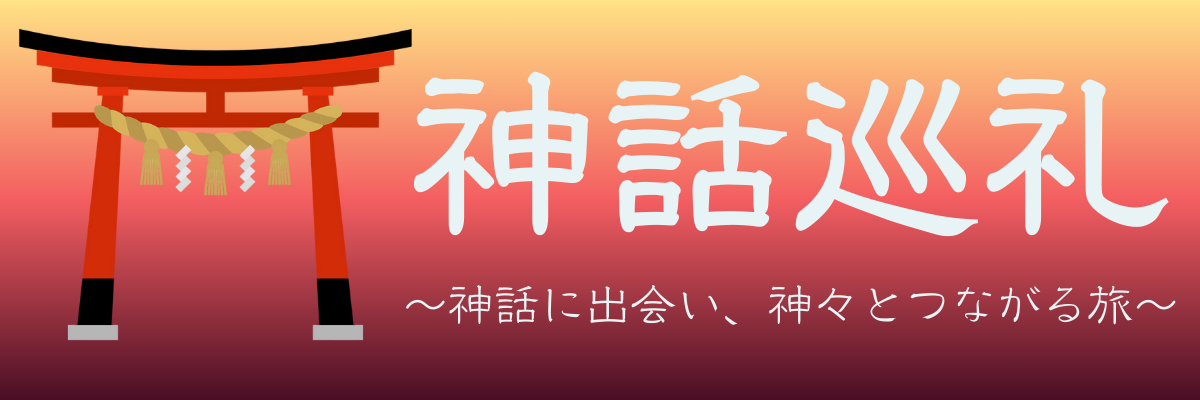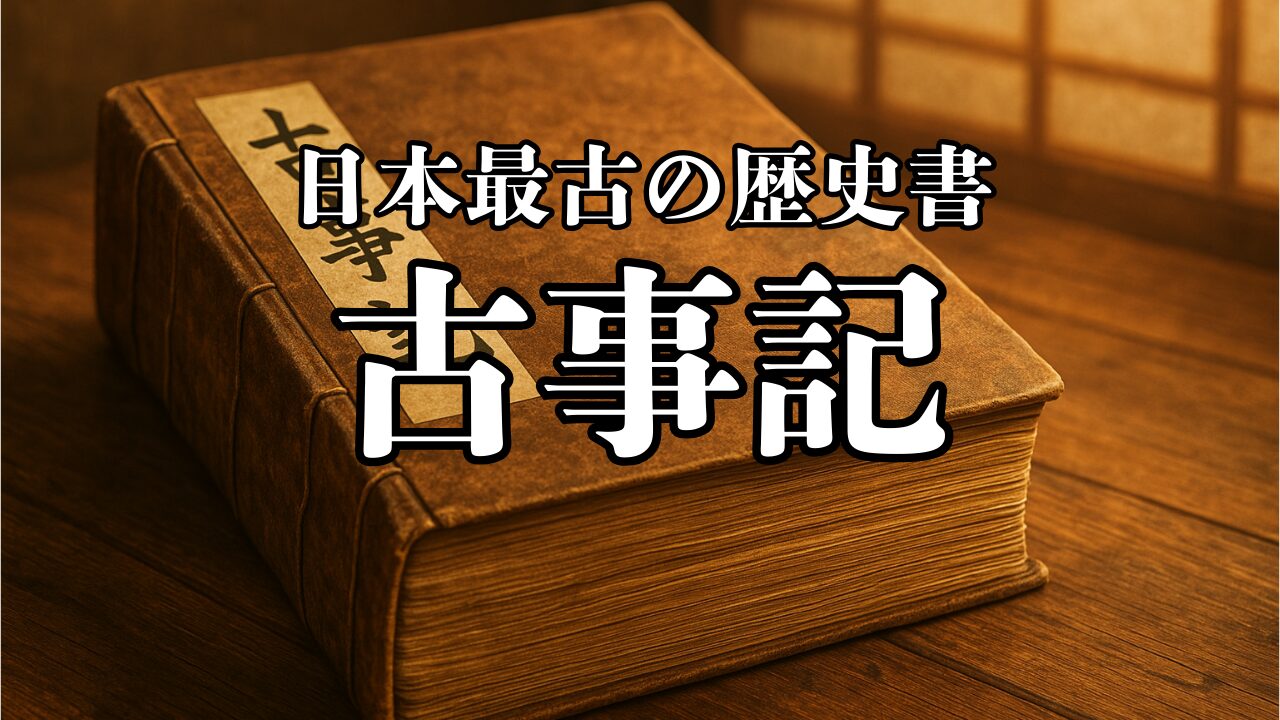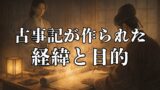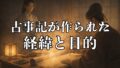この記事では、「古事記(こじき)」とはどのような書物なのか。
また神道とどのような関係を持っているのかを、歴史的背景をふまえながら初心者向けに解説します。
「古事記」という言葉に対して、学校で習った歴史の一場面や、神様の物語がまとめられた神話集といったイメージを持っている方も多いかもしれません。
実際に古事記は、712年に編纂された日本最古の歴史書とされています。
天地のはじまりから神々の物語、そして初期の天皇の系譜までが記された、非常に特徴的な構成を持つ書物です。
一方で、古事記は単なる歴史資料にとどまりません。
神社に伝えられてきた神話や、祝詞(のりと)の言葉、祭祀の考え方など、神道文化の背景を理解する手がかりが多く含まれています。
古事記を読み解くことは、神道が大切にしてきた世界観や価値観を知る一つの視点になるとも言えるでしょう。
本記事は、特定の信仰を勧めるものではなく、日本神話や古代日本の文化を理解するための参考情報としてまとめています。
文化や思想を知る入り口として、気軽に読み進めていただければ幸いです。
古事記とはどんな書なの?
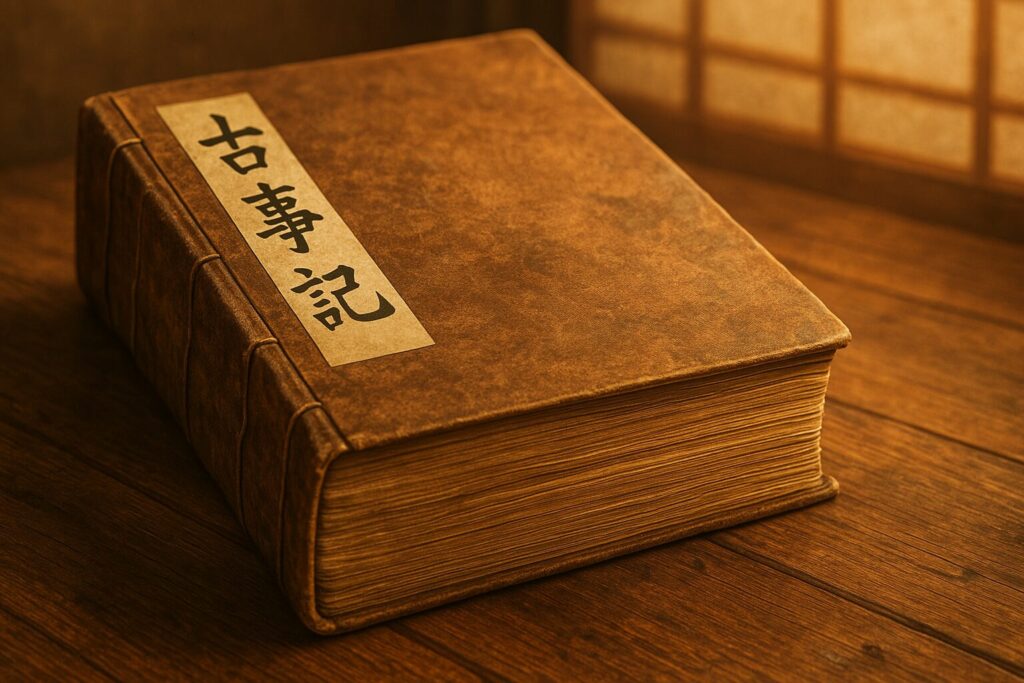
古事記は三巻から構成されています。
- 上つ巻(神話)
天地創生から始まり、伊邪那岐命と伊邪那美命の国産み、天照大神や須佐之男命など有名な神様の物語、初代天皇誕生など、いわゆる「日本神話」の部分が語られています。 - 中つ巻(初代~15代天皇まで)
初代天皇の神武天皇の東征から始まり、15代天皇の応神天皇までが描かれています。
日本という国家が形づくられていく過程を描いた建国の物語です。 - 下つ巻(16代~33第天皇まで)
16代天皇の仁徳天皇から33代天皇の推古天皇までのお話です。
つまり古事記は、天地のはじまりから神々の物語、天皇の系譜までが記された、日本古代の世界観を知るうえで重要な書物なのです。
古事記と神道はどのようにつながっているのか

古事記の神話は、神道の祭祀や世界観と深い結びつきがあります。
- 禊ぎ祓いの起源
伊邪那岐命が黄泉の国から戻り、川で穢れを祓ったことに由来しています。
神社に行くとまず行う「手水舎で手を洗う」などの清めの儀式は、この神話が原点になっています。 - 神楽(かぐら)の起源
雨岩戸神話をご存じだろうか?天照大神が岩戸に隠れ、世界が闇に包まれた物語です。
このとき神々が岩戸の前で踊ったことが、神楽の起源とされています。 - 出雲大社の起源
出雲の大国主が国土を譲る物語。今も出雲大社の祭祀に息づいています。
このように古事記を学ぶと、神社参拝や祭りなどの意味がより深く理解でき、今でも神道というものが「生きる文化」であることがわかりますね!
今こそ古事記からの学びが大切な理由
古事記は単なる古代の物語ではありません。
むしろ現代を生きる私たちに、大昔の知恵を授け、問いかけてくる書物だと思います。
私たちが神社で手を合わせるとき、そこには古事記の神話があります。
「なぜこの神社にこの神様が祀られているのか…」その答えを知ることで、より神様とのつながりも強くなります。
そこに描かれる神々は、喜び、怒り、迷いながらも最終的に調和を選びます。
その姿は、争いや分断が絶えない現代社会で
「人と人とのつながり」「自然と人との調和」などを思い出させてくれる教科書のようです。
さらに古事記に登場する神々は太陽や水、大地といった自然そのものです。
日本古来の自然を神として敬う考え方は、環境破壊や気候変動の時代を生きる私たちに「共生とは」というメッセージを伝えてくれています。
古事記は、日本最古の歴史書であると同時に、神道の神話や世界観を伝える大切な書物です。
古事記を読むことで、自らの生き方を見つめ直すきっかけになるかもしれません。
まとめ
古事記は、日本神話や神社文化を読み解くうえで、背景となる考え方や世界観を伝えてくれる資料の一つです。
その成立の経緯や構成を知ることで、神話に登場する物語や神々の描かれ方も、これまでとは違った視点で捉えられるようになるかもしれません。
本記事が、日本神話や古代日本の文化に触れる最初の入り口として、気軽に親しむきっかけとなれば幸いです。
次回予告
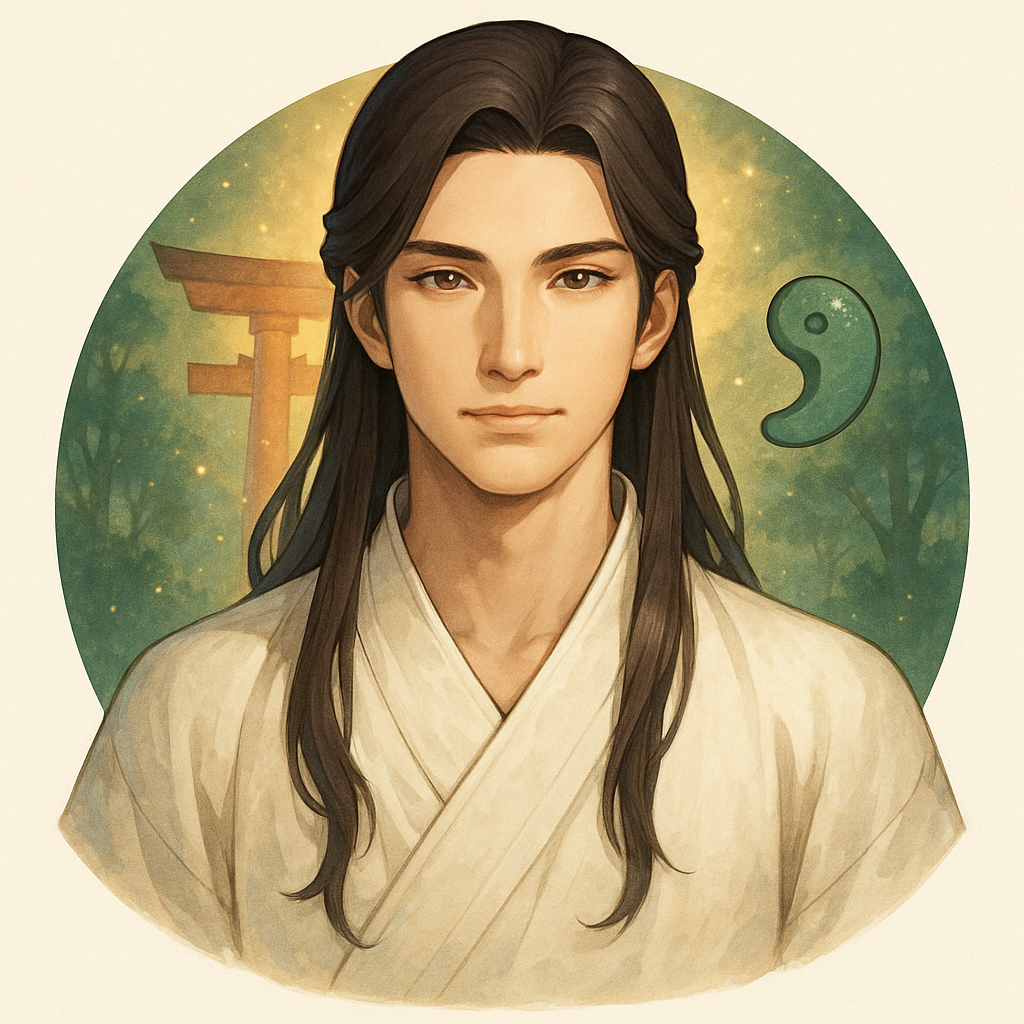
次回は「古事記は誰が、どのようにして作ったのか?」その成立の背景に迫ります!